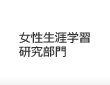|
|

- 学長
- 向井 剛
- 国際文理学部 国際教養学科
- 教授大久保 順子
- 教授木村 貴
- 教授坂本 浩一
- 教授佐藤 秀樹
- 教授ぱすましり じゃやせーな
- 教授鈴木 有美
- 教授徐 阿貴
- 教授長岡 真吾
- 教授野依 智子
- 教授橋本 直幸
- 教授馬場 優
- 教授深町 朋子
- 教授吹原 豊
- 教授Sven HOLST
- 教授宮川 美佐子
- 教授宮崎 聖子
- 教授村長 祥子
- 教授渡邉 俊
- 准教授石神 圭子
- 准教授岩下 真澄
- 准教授河原 梓水
- 准教授金 希京
- 准教授小西 鉄
- 准教授近藤 洋平
- 准教授坂口 周
- 准教授柴田 聡
- 准教授白新田 佳代子
- 准教授朴 紅蓮
- 准教授増山 みどり
- 准教授山根 健至
- 講師梶田 知沙
- 講師塚野 慧星
- 講師Robert PRESLAR
- 国際化推進センター
- 准教授高原 芳枝
- 言語教育センター
- 教授Nigel STOTT
- 講師田上 優子
- 講師都地 沙央里
- 講師Andrew THOMPSON
- 講師Amy TOMS
- 講師Andrew GALLACHER
- 講師Sorrell YUE
- 講師Eric MILLER
| 福岡女子大学地域連携センター 〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1 Tel:092‐661‐2728(直通) Fax:092‐692‐3220 | Copyright c 2012 福岡女子大学 地域連携センター All Rights Reserved. |