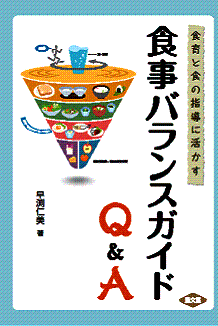教 授 の 紹 介
教 授 の 紹 介
国際文理学部 食・健康学科/大学院人間環境学研究科/公衆栄養学(栄養指導学)研究室/教授
医学博士 管理栄養士 |
専門は、栄養健康科学(公衆栄養学・実践栄養学) |
食教育や栄養改善に必要な基礎的研究とともに、住民を対象にした調査や栄養・食教育、スポーツ選手の栄養指導、食事バランスガイドの普及啓発、産官と連携した食育や健康づくりのための食環境整備等、実践的研究・活動も行っている。 |
日本栄養改善学会理事、日本健康栄養システム学会理事、日本高血圧学会チーム医療委員会委員、日本食育学会企画委員、厚生労働省・農林水産省フードガイド検討会委員、福岡県青少年アンビシャス運動委員会委員、大牟田市食育推進会議会長、福岡市食育推進会議委員、元福岡ソフトバンクホークス栄養アドバイザー等。 |
|
| <最終学歴> |
九州大学大学院医学研究科博士課程社会医学 |
| <学位・資格> |
医学博士(九州大学) |
| 家政学修士(お茶の水女子大学) |
| 管理栄養士,高等学校家庭科専修免許 |
| <所属学会> |
| 日本栄養食糧学会,日本栄養改善学会 |
| 日本高血圧学会,日本健康栄養システム学会 |
| 日本公衆衛生学会,日本疫学会 |
| 日本栄養学教育学会,日本食育学会 |
| 日本食生活学会,日本栄養アセスメント研究会 |
| 九州代謝栄養研究会,日本調理科学会 |
| 日本家政学会,国際家政学会 |
| <委員等社会活動> |
福岡ソフトバンク(ダイエー)ホークス 栄養アドバイザー (1988〜) |
| 福岡市スポーツ振興審議会 委員 (1994〜) |
| 福岡市健康づくり研究委員会 委員 (1995〜2013) |
| 青少年アンビシャス運動委員会 委員 (2001〜) |
| 管理栄養士国家試験 委員(2001〜2010) |
| 福岡女子大学食育ボランティア学生ネットワーク 顧問 (2003〜) |
| 厚労省・農水省フードガイド(仮称)検討会 委員 (2004〜) |
| 福岡県スポーツ振興審議会 委員 (2005〜11) |
| 科学研究費委員会 専門委員 (2005〜09) |
| 福岡市食育推進会議 委員(2006〜) |
| 親子で楽しむ朝ごはんコンクール 審査委員長 (2006〜11) |
| 農水省食育コンクール推進委員会&コンクール 審査委員 (2007〜10) |
| やずや食と健康研究所助成 評議委員 (2007〜) |
| 福岡女子大学食育支援プロジェクト 代表 (2007〜) |
| 福岡市水産業振興審議会 委員(2008〜) |
| 福岡発食育&食環境整備ネットワーク 会長 (2008〜) |
| 科学研究費補助金新学術領域研究「研究課題提案型」 審査員 (2008〜09) |
| 大牟田市食育推進計画策定協議会 会長 (2009〜10) |
| 「日本人の食事摂取基準」活用検討会作業部会 委員 (2009〜10) |
| 特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会 書面審査員 (2009〜12) |
| 福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証委員会 委員 (2009〜) |
| 健康運動実践指導者養成講習会 講師 (2009〜) |
| 文科省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会 専門委員 (2010〜12) |
| 大牟田市食育推進会議 会長 (2010〜) |
| 福岡県地域保健従事者人材育成検討委員会 委員 (2012〜) |
| 日本栄養改善学会 理事 (2012/11〜) |
| 日本健康栄養システム学会 理事 (2012/12〜) |
| 日本栄養改善学会九州・沖縄支部 幹事 (2013/7〜) |
| 管理栄養士国家試験 委員・総務委員 (2013/8〜) |
| 第62回日本栄養改善学会学術総会 会長 (2013/9〜15/9) |
| <専門分野> |
| 栄養健康科学(公衆栄養学・実践栄養学) |
| <主要研究課題> |
| 1.生活習慣病予防のための食環境整備と減塩の効果検証 |
2.食育推進のための教育手法やツール(教材)の開発と有効性の検討 《食生活セルフチェックはこちら》 |
| 3.保育所・学校・職域・地域等における食育・実践栄養学研究 |
4.スポーツ選手の健康管理と栄養教育手法の研究 |
| <担当授業科目と内容> |
| 実践栄養活動論:食・健康学科新入生対象の公衆栄養学概論と実践栄養活動について |
| 栄養マネジメント論:栄養ケア・マネジメントの基礎と概念と実際の活動について |
| 公衆栄養学:公衆栄養活動の企画・実施・評価に必要な知識・情報について |
| 公衆栄養学実習:栄養アセスメント(身体状況・食事状況・生活状況の把握)実習 |
| 公衆栄養学臨地実習:保健所実習(公衆栄養活動)調整・計画・指導・評価等 |
| 臨地実習事前事後指導:保健所・病院・小学校実習の事前事後指導 |
| 食・健康科学基礎演習:栄養指導の実際(カウンセリングやスピーチ)の英文を読み解く |
| 食・健康科学総合演習:栄養指導関連の文献抄読、実践栄養学演習、実践栄養活動 |
| 栄養指導学特論(大学院):食教育・栄養改善のための実態把握・判定・指導方法 |
| 栄養指導学特別演習(大学院):食教育・栄養改善研究に必要な文献収集と抄読 |
| 栄養健康科学卒業研究指導:4年生4名 |
| 栄養健康科学特別研究指導(大学院):修士課程1年生3名、修士課程2年生以上5名 |
次世代の食育における減塩への取組み
〜「和食文化の継承」と「減塩」〜
「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、「日本の伝統的な食文化」を見直し継承しようという機運が国内外で高まっています。日本人は長寿で肥満は少ないものの、食塩摂取量は依然として多く、高血圧者が多いのが現状です。2013年世界保健デーのテーマに高血圧が選定され、WHOは塩分摂取の新ガイドラインを発表、減塩への取り組みが国際的課題となっており、和食文化の継承には減塩が不可欠になっています。そのための取り組みと食環境整備の必要性について、以下のような内容を中心に紹介しています。
1.栄養バランスが優れた「日本型食生活」の課題と対策
2.「美味しい減塩弁当で無理なく減塩」の試みと検証
3.減塩品と従来品の二重盲検官能評価の試みと検証
4.食環境整備の必要性
今後は、食事バランスガイド等を活用して望ましい日本型食生活の実践を促すとともに、食塩量を考慮した健康な食事が選べるような食物と情報を提供する食環境を整備するなど、生活習慣病予防に役立ち、健康寿命の延伸とQOLの向上につながる食育が推進されることを願っています。
(「保健の科学」平成26年3月号特集
「今,改めて,日本における減塩対策を考える−健康寿命の延伸に向けて」より)
<食育のすすめ>
日本人の 2003年の平均寿命は、女性85.33歳、男性78.36歳、日本は世界に冠たる長命国になりました。しかし、日本人全てがその寿命を全うし、幸せな人生を送っているわけではありません。過剰なストレスによる自殺者や生活習慣病等による寝たきり者の増加は、深刻な問題です。全ての人が健やかで心豊かに生活できる、真の「長寿」社会にすることが私たちの課題です。
栄養・食生活の分野では、 2000年3月厚生労働省が「健康日本21」の中で、栄養状態を良くするための適正な「食物摂取」、そのための「行動変容」、それを支援する「環境作り」の目標を掲げ、3省(厚労省・農水省・文科省)合同で「食生活指針」が策定されました。2003年5月には基本的な方針を定めた「健康増進法」が施行され、総合的な推進が図られています。今春からは学校教育に栄養教諭制度が導入され、給食だけではなく食に関する指導が行われることになっており、「食育基本法」制定の準備も進んでいます。
食育基本法は、心身の健康増進と豊かな人間形成、食に対する感謝の念の醸成、伝統的な食文化等への配慮、食の安心安全の確保等を基本理念としています。最近は食と身体との関わりが重視され、心との関わりや文化・社会・環境との関わりが軽視される傾向にあります。しかし、食は身体の健康だけでなく、心の健康にも大きく関わっており、健全な社会と環境の保持にも影響を与えます。「何を食べるか」だけでなく「どのように食べるか」という「食のあり方の本質」を見直す時期にきていると思います。
栄養や食事に対する無関心が、不適切な食物摂取や不規則な食生活となり、心身を不健康にして社会の活力を低下させ、さらに食料自給率の低下や環境破壊にも影響を与えていることに留意したいものです。自分の行動の選択は自己責任ですが、より良い選択ができるように、適切な情報と知識を提供する環境を整備することが望まれます。特に、次世代を担う子どもが健やかに生まれ、育つように、子どもを生み育てる若者たちが、栄養や食事に関心を持ち、正しい知識と情報に基づく適切な食の選択をして欲しいと思います。
食生活は自分だけの問題ではなく、次代の社会にも影響を与える大切な日々の営みです。また、一生懸命頑張った後の食事はご褒美であり、何より楽しみなものです。食べる喜びを感じることで、「良い一日だった」「生きていて良かった」「家族って良いなあ」というような、安らぎや幸福感を覚えます。これからのストレス社会を生き抜く心身の原動力となる「楽しい食卓」を目指した「食育」が必要です。
(「小児歯科臨床」Opinionより 2005.3)
『だれでもわかる・だれでも使える
食事バランスガイド』を発刊!
「食事は、生きるために必要であると同時に.楽しむために必要なもの。一生懸命頑張った後の食事はご褒美であり、何より楽しみなものです。食べる喜びを感じることで、 “今日もいい一日だった”“生きていて良かった”という安らぎや幸福感を覚えます。そのような食事を共にする家族は何より大切なものであり、楽しい食卓があれば、家庭崩壊などは考えられません。心身の健康には“何を食べるか”だけではなく、“どのように食べるか”が大きく関わっているからです」
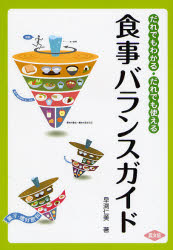
私たちが1日に「何を」「どれだけ」食べたらいいのか、望ましい食事のとり方とおおよその量を分かりやすく示した逆三角形のコマ型のイラスト、それが食事バランスガイド。厚生労働省と農林水産省がこの「日本版フードガイド(食事バランスガイド)」を策定した時、検討会の委員を務めたのが早渕さんです。
縦割り行政の中で、省が合同でつくった日本版フードガイドは、食品ではなく、食文化を表す料理で示しているのが特徴。世界に誇れる画期的なものです。そのフードガイドを、一人でも多くの方に知ってほしい、食環境整備に役立ててほしいという思いから、今回、この本を作りました」
中身は、自身の食の体験から、食事バランスガイドの見方・使い方、自分や家族のための簡単活用術まで。賢く選んでおいしく食べるためのポイントやアドバイスが満載です。
(「西日本リビング福岡中央」より 2008.3)
食育と食の指導に活かす
『食事バランスガイド Q & A 』が登場!
小中学校や幼稚園・保育園など食育の場で、あるいは、地域・健康づくり活動の場で、さらにフードビジネスの最前線に立つ人のために、専門家として「食事バランスガイド」をどのように理解し、指導に活用したらよいか、Q&A 方式でわかりやすく解説!

食事バランスガイドを
一緒に活かしましょう!
農林水産省「平成20年度
にっぽん食育推進事業」
食育五輪2008inふくおか
福岡発食育&食環境整備ネットワーク
詳しくはこちら!