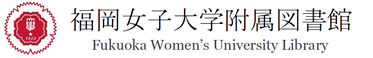本の紹介
本の紹介

3月14日と言えば「ホワイトデー」が有名ですが、「円周率の日」「数学の日」「πの日」などの数学に関係する記念日がいくつもあります。これらの記念日は「314」という円周率の数字にちなんで制定されました。
みなさんは数学にどのようなイメージをもっていますか。難しい、役に立たない、嫌いといったマイナスのイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。一度持った苦手意識を払拭することは容易ではなく、学校の授業や試験での嫌な思い出を引きずってしまいがちです。今回は、そんな数学への意識が変わるような楽しい数学本を3冊紹介します。
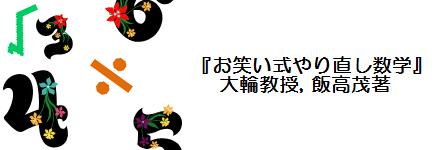
「本書は数学が嫌いという人を対象に書かれた数学お笑いの本である」(p.4)とまえがきにある通り、数学が嫌いな人が楽しんで学びなおせる数学の入門書です。本書ではお笑い芸人である大輪教授が 中学1年~3年の数学ほぼすべてのカリキュラムをお笑いのネタとしてさらい、数学者である飯高茂がツッコミを入れながら解説をしています。たとえば「サザエさん」を素因数分解したり、「ドラマのような恋をする」確率を計算してみたりと、数学とまったく関係がないようなものを例に説明をしているので、少しは数学を身近に感じる事ができるのではないでしょうか。数学に苦手意識のある人にこそ読んでもらいたい1冊です。
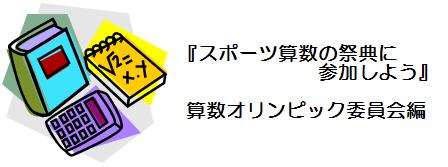
世界中の数学が好きな少年少女のための、「国際数学オリンピック(International Mathematical Olympiad) 」という大会があります。高校生を対象とした国際大会で、もちろん日本からも参加して、毎年上位に入賞しています。この大会より低い年齢を対象としているのが「算数オリンピック」です。こちらは日本国内の大会で、多くの小学生が参加し、国際数学オリンピックの登竜門となっています。
本書には過去の大会で出題された問題と解説、答えが掲載されています。出題は小学校の教科書の範囲からですが、子ども向けだと甘く見てはいけません。柔らかな発想力と鋭い洞察力が必要とされる難問ばかりです。頭を柔らかくしてぜひ挑戦してみてください。

「和算(わさん)」という日本で独自に発達した数学をご存知でしょうか。様々な文化と共に中国から日本に入ってきた算術(数学)は、江戸時代には武士や町人ら身分に関係なく多くの人が学び、発展しました。明治以降は西洋数学が主流となってしまいましたが、江戸時代には和算書が何冊も 出版されベストセラーになるほど流行していました。
本書は安永4年(1775年)に刊行された『算法少女』という和算書を題材にして書かれました。決して難解な数学の本などではなく、算法が得意な少女「あき」がその才能からある事件に巻き込まれるという物語です。本書を読んで和算の魅力を知るうちに、数学に対するイメージが変わるのではないでしょうか。
[ 前に戻る ]